日本のキノコ生産業界は、安定した需要と高度な技術力に支えられてきました。
長野県は、いくつかの要因が重なったことから、全国的にキノコ生産の一大拠点となってます。
- 自然環境の適性: 長野県は冷涼な気候と豊富な水資源に恵まれており、キノコの栽培に適した環境が整っています。特にエノキタケやブナシメジなどの施設栽培において、安定した気候条件が重要です。
- 歴史的背景: 昭和30年代にエノキタケの人工栽培が普及し、冷房設備の開発により通年栽培が可能になりました。これにより、冬場の副業から通年の専業へと移行し、地域全体でキノコ栽培が盛んになりました。
- 産業基盤の整備: 長野県には「ホクト株式会社」のような大手企業が拠点を構え、研究開発や生産技術の向上に取り組んでいます。このようなリーディングカンパニーの存在が、地域全体のキノコ産業を支えています。
- 地域の連携: 地元の農協や関連団体が生産者を支援し、販売ルートの多様化や価格競争力の向上を図っています。これにより、地域全体での生産効率が向上しています。
その結果、長野県は国内売上高のシェア約34.4%とトップに君臨し、2位の新潟県(約21.6%)、3位の福岡県、4位 北海道、5位 宮崎県と続いております。
キノコの生産は栽培や収穫だけでなく加工や流通工程など、その影響は幅広く、地域に多くの雇用機会を提供でき、山間部や農村地域では重要な収入源となってます。
特に「信州きのこ」などとして地域ブランドの形成に成功した結果、「キノコ狩りイベント」を観光客向けに開催し、地元飲食店の活性化に一役を買ってます。
しかし近年では、生産コストの増加や市場価格の低迷が課題となっており、倒産するキノコ関連企業も増えています。
本記事では、有限会社マルヨの倒産を例に業界全体の課題を整理し、リーディングカンパニーであるホクト株式会社との比較を通じて、中小規模のキノコ生産者が直面する現実と未来について考察します。
 パンチです
パンチですどうぞ最後までご覧くださいね
有限会社マルヨの倒産について
企業概要 有限会社マルヨは1991年に創立された、長野県で「えのきたけ」の施設栽培を行う中小規模の企業であり、高度な液体種菌技術を採用していました。
倒産の背景 2024年4月、マルヨは負債総額約14億5,000万円を抱えて民事再生法の適用を申請しました。その理由は以下の通りです
- 多額の設備投資による借入金の負担。
- キノコ相場の低迷による収益の悪化。
- 生産調整が難しく、市場価格に合わせた出荷対応が困難だったこと。
この倒産は地域経済に雇用不安を招いただけでなく、キノコ生産業界全体の将来に課題を投げかける事例となりました。
リーディングカンパニー 「ホクト株式会社」の戦略
ホクトの強み
プライム市場への上場企業であるホクト株式会社は、財務的にも安定しており、施設栽培を徹底的に管理することで安定した供給を実現しています。
また市場の需給動向に応じて柔軟な「生産調整が可能」な点を行える体制が整っていることが同社の大きな武器です。
さらに、研究開発に力を入れ、グローバル市場への展開を進めることで多角化を図っています。
赤字決算の実例
しかしながら、ホクトでも2023年3月期には約2.9億円の赤字を計上しています。
この原因には「燃料費や電気代の高騰」を筆頭に、「市場価格の変動」、「国内外の消費動向の影響」などが挙げられます。
大規模企業のホクトでさえ赤字に転ずる時があるのですから、キノコ事業が直面しているリスクが大きいことが分かります。
中小規模のキノコ農家が抱える課題
課題の概要
中小規模のキノコ農家は以下の点で経営が厳しい状況にあります。
- 設備投資の負担が大きく、相場変動への対応力が乏しい。
- 生産調整が困難で、収益を確保するためには低価格でも出荷を続けざるを得ない。
- 地元市場への依存度が高く、価格競争の激化にさらされる。
一般的な菌床栽培の場合、100坪の栽培ハウスを新築するには1000万円以上が必要となり、これにプラスして金賞を調達するコストが必要となります。
私の感覚では設備投資にかかる費用は「野菜<果樹<キノコ<コメ」といった順位になりそうですね。
実は私が新規就農時に「キノコ一緒にやる?」と誘われたのですが「とりあえず見送ります」と答えた記憶があります。
解決への提案
- 統合や資本提携などによる経営基盤の安定化。
- 地域ブランドの構築を通じた差別化。
- 高付加価値商品の開発と販売。
- 農協や地域連携を活用した販売ルートの多様化。
結論です
有限会社マルヨの倒産は、中小規模のキノコ農家が直面する現実を浮き彫りにしました。
ホクトのような大企業も2023年3月期決算では営業赤字を経験してます。
キノコ事業は「工場」的なイメージもありますが、一般的な農業と同様に安定的ではないことがハッキリしました。
近年では燃料費や電気代の高騰、キノコ価格の低迷などが全国的に影響を及ぼし、2024年には国内でキノコ生産業者の倒産が13件発生しました。
これからのキノコ生産者には、生産規模に応じた柔軟な経営戦略と、地域連携を活かした持続可能な取り組みが求められます。
キノコ生産者に求めすぎるのは酷ですが、過疎化が進む地方都市、しかも山間部において「基幹産業」と位置づけられている場合、一つの会社が倒産することで多くの雇用者や地元の飲食業などへ影響が出てしまいます。
日本のキノコ産業が持続的な成長を遂げるためには、現状を見据えた革新と協力が必要です。




最後までご覧頂き有難うございました
キノコは涼しいところで作られているんですね。
皆さんが好きなキノコ料理は何ですか?
私はキノコたっぷりの「鶏すき焼き」です!
是非ご意見やご感想もお聞かせ下さいね

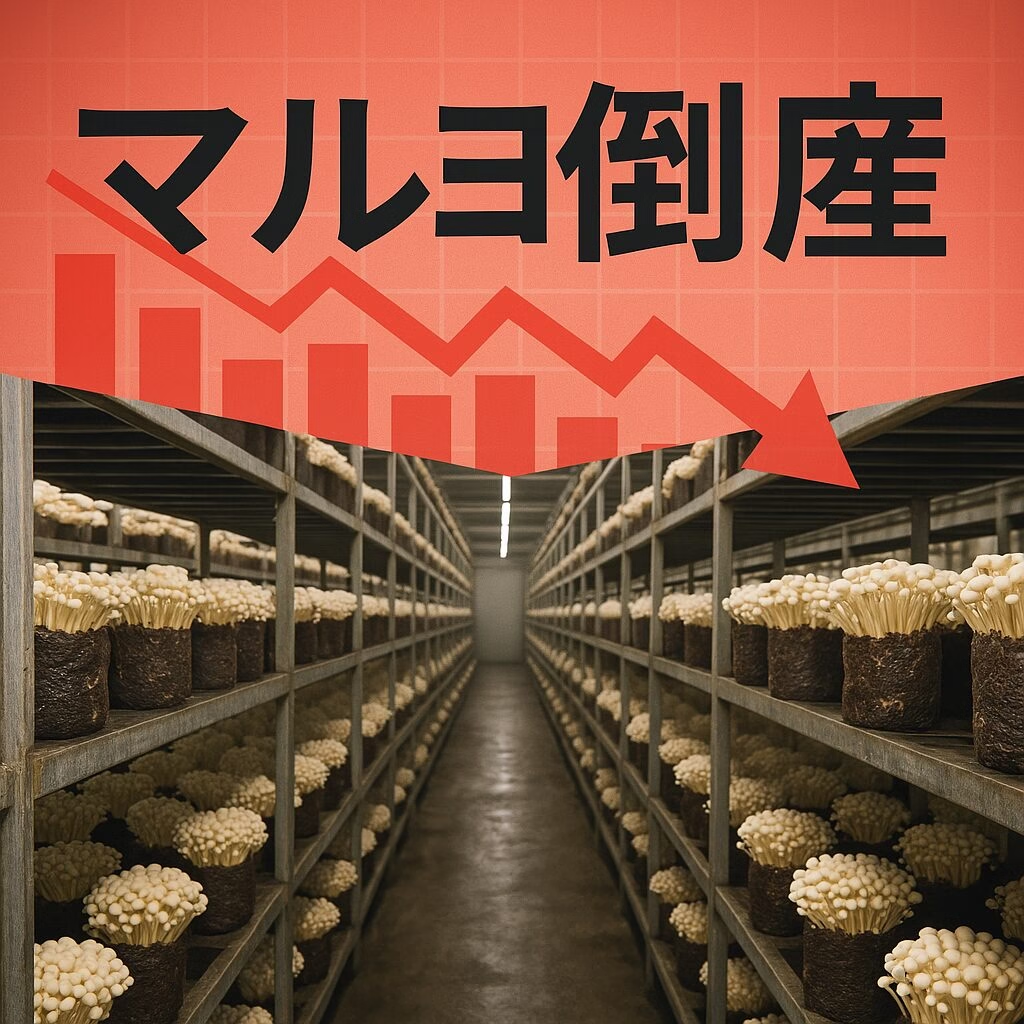


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46a09297.97902e0d.46a09298.6ee99432/?me_id=1203580&item_id=10000202&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdrmori1%2Fcabinet%2Fitems%2F03220%2F03220thum_v2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント