株式会社茶の木村園は、茨城県つくば市で1948年に創業された老舗お茶販売店でした。
静岡県掛川市産の深蒸し茶「とろりん茶」を中心に販売し、地域住民や観光客から愛されていましたが、2025年1月31日、事業を停止し、破産申請の準備に入ることとなりました。
 パンチです
パンチです最後までご覧くださいね
静岡茶の販売で築いた信頼と地域への貢献
株式会社茶の木村園は、静岡茶の高品質を地域の消費者に届ける役割を果たしてきました。
特に同社が取り扱う深蒸し茶「とろりん茶」は、その濃厚な味わいと健康効果で多くの顧客に支持されていました。
また、地元つくば市では「かき氷」の販売でも知られており、地元の文化や観光の一部を担っていた存在でもありました。
倒産の背景に潜む複雑な要因
木村園の売上推移は以下の通りです。
- 2019年(最盛期): 売上は約1億2100万円
- 2020年(コロナ禍開始): 売上が減少し、約9500万円(前年比22.5%減)
- 2021年: コロナ禍の影響が続き、売上は約8500万円(前年比11.5%減)
- 2022年: 徐々に回復の兆しが見られ、約9200万円(前年比8.2%アップ)
- 2023年: 売上は約9983万円でしたが、333万円の赤字を計上(前年比8.5%アップ)
- 2024年: 売上がさらに減少し、約8000万円以下と推定されています’前年比20%以上減)
倒産に至った原因には、いくつかの複雑な要因が絡んでいました。
- 東日本大震災による風評被害 福島第一原発事故により、静岡県の茶葉から微量の放射性物質が検出される事例がありました。この結果、消費者の間で静岡茶の安全性への懸念が広がり、全国的な風評被害が発生。木村園もその影響を受け、売上に打撃を受けました。
- コロナ禍による市場変化 新型コロナウイルスのパンデミックは、木村園にとって致命的な課題をもたらしました。葬儀の小規模化により、返礼品としての茶葉需要が減少。また、観光客の減少が店舗の売上に直接的な影響を与えました。さらに消費者の購買行動がオンラインへ移行する中、木村園は店舗中心の販売スタイルを維持していたため対応が遅れました。
コロナ禍により葬儀が小規模化し、返礼品としての茶葉の需要が大幅に減少しました。これにより、木村園の売上の一部を支えていた重要な市場が縮小しました。
またコロナ禍で多くの消費者がオンラインショッピングに移行した一方で、木村園は主に店舗販売に依存しており、オンライン販売の強化が遅れていた可能性があります。
地域の伝統的な企業が残す教訓
木村園の倒産は、地域の伝統的な企業がいかに外部要因に左右されるかを示しています。
風評被害や社会的変化は企業存続を脅かす可能性があります。
さらに、パンデミックの影響で消費者行動が劇的に変化する中、企業は迅速に対応しなければならないという教訓を残しました。
また、地元の伝統や文化を支える企業の存続には、地域社会全体が関与することの重要性が浮き彫りになりました。
地元消費者や自治体による支援や共同体としての取り組みが、同様の課題に直面する他の企業にとって希望となるかもしれません。
株式会社茶の木村園の物語は、地域と伝統のつながりを尊重する一方で、現代の市場環境に適応する必要性を私たちに教えてくれます。
具体的には宇治茶の老舗茶舗の多くは、本店だけではなく煎茶だけではなく抹茶やスイーツなどを提供するテイクアウトも可能な販売網も観光地や都市部の百貨店に整備することで、消費者にいわゆる顔が見える営業を展開してます。
そこで知名度を上げつつ、楽天市場などのネット販売で売上を確保しているのです。
木村園の倒産は一つの終焉ではありますが、新たな始まりへの糧として活かされるべき教訓を多く含んでいます。
私が静岡県民だとして郷土自慢の掛川茶が遠く茨城県で売られていたら悪い気はしないですが、静岡の仲間に「木村園の掛川茶」を選ぶことはネタ以外ではありえないですね。
恐らく他の県からの観光客やネット通販愛好家も同じだろうと思います。
売り上げ規模も小さかった木村園が独自に経営を立て直すには、地元密着で「かき氷」を売っても「焼け石に水」だったことでしょう。
資本も販路も小さ過ぎたと言わざるを得ず、「伝統の深蒸しの技術」を持っていても、どこからも資本提携や救済の声が掛からなかった…、それが答えだと思います。
残念ですが、今のお茶市場の厳しい競争から察すると、この結果は必然だったと言わざるを得ないです。
まとめ
倒産の背景には、東日本大震災による風評被害、新型コロナウイルスの影響による葬儀需要の減少、観光客の減少、オンライン販売への対応の遅れが挙げられます。
さらに、資金繰りの悪化や業績の低迷が重なり、経営を維持することができませんでした。
この事例は、地域の伝統的な企業が市場環境や消費者行動の変化に対応する重要性を教えてくれます。
地元密着型のお店を本当に守りたいのであれば、時代の流れに逆らってでも、継続的にそのお店を利用することが求められます。
閉店セールのときだけ訪れて涙を流する客や、それを映像で流すオールドメディアの報道スタイル、彼らは本当にこの店や地元の文化に愛着を持っているのか疑問を覚えてしまいます。
木村園が残した歴史と教訓を、これからの経営に活かしていきませんか?
私たちにとって価値のある地域文化や老舗が身近にあったとしても、「少し高くても地元のお店を支えたい」と多くの消費者が思わなければ、結局その伝統は消えてしまう運命にあるのです。
将来後悔しないため、私は応援する会社の商品を買って、良いものだけを紹介するスタイルをこれからも継続していきたいな、って私は思います‼
追記 「株式会社堤園」の事業停止
群馬県前橋市に本社がある「株式会社堤園」は1931年に創業し、1952年に法人化された老舗企業で、主に日本茶や海苔製品を冠婚葬祭用の返礼品として卸売りしていました。
ピーク時には年間売上高約6億円を記録するなど、「木村園」と同様に地域における一定の知名度を誇っていました。
しかし贈答品需要の低迷や市場環境の変化による競争の激化のため「堤園」の売上が低迷。借入金の返済負担が財務を圧迫した結果、2024年12月5日事業停止を決定しました。負債総額は約4.9億円とのことです。
このように全国の「お茶の卸・小売業」は例外なく苦境に立たされており、特に「非有名産地」でのみ営業する中小規模の会社や店舗は、今後加速度的に淘汰されるものと思われます。
追記 茶器販売会社の倒産
京都府亀岡市に拠点を置く「京都茶華道具館株式会社」は手ごろな価格の茶器販売を主な業務としていましたが、2025年3月21日に破産手続きが開始されました。
茶道や華道を嗜む人が近年減少傾向にあることが原因と推察されます。
かつて茶道人口は400万人を超えていましたが、2018年時点で220万人にまで減少しているとのことです。
竹田理絵さんの著書を紹介する中で「お茶の家元」が稽古に留まらずにゲリライベントや海外での講演・実演、また京都福寿園などの老舗茶舗各社も茶文化を盛り上げるために様々な取り組みをしていることは間違いない事実です。
ただ残念なことに現代の茶華道は日本の経済が失速した影響をモロに受けているようです。
それに加えて女性の社会進出が進んだことや趣味の多様化など、様々な原因が交錯した結果、以前よりも本格的に取り組むハードルが上がっているように思えます。
追記 大資本の抹茶事業への参入
私が趣味としてのお茶を始めてから初の春の季節を迎えるのですが、このタイミングで飲食店・コンビニ各社が抹茶の季節限定品を出すことに驚いてます。
(だって新抹茶の季節は11月だから、季節外れなんですよっ!)
ミスタードーナツの祇園辻利とのコラボを筆頭に、マクドナルドでは「宇治抹茶フラッペ」、ファミリーマートでは「抹茶withフルーツ」というテーマで「抹茶とイチゴのティラミス」などが提供されます。



出典:ミスタードーナツ公式ホームページ
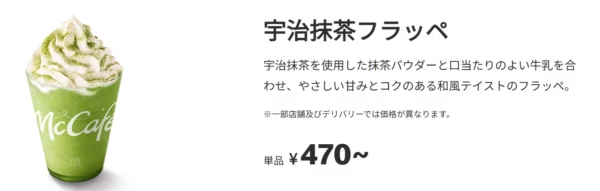
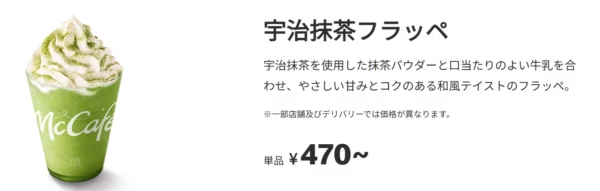
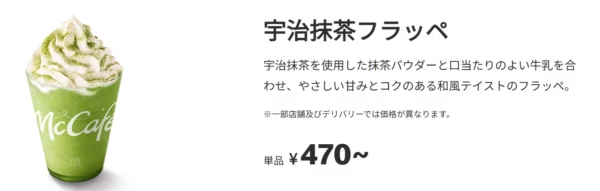
出典:マクドナルド公式ホームページ



出典:ファミリーマート公式ホームページ
きっと季節限定の話題の商品を取り扱うお店に消費者は足を運ぶでしょう。
皆さんはこの中のどれか試してみたくなるものはありましたか?
ただ…老舗の有名茶舗にとって、この大資本の攻勢は抹茶の認知度がアップする以上に経営にとって逆風となりえます。
有名産地でないお茶の関連業者にとっては、なおさら大きな逆風であろうかと思います。
この時期にお茶を購入して下さるお客さんは大変有難いものだと思います。
皆さんが応援するお店のために行動するなら「今」がベストですよ。




最後までご覧頂き有難うございました。
皆さんのご感想やご意見、いつも楽しみにしてます。
どうぞお気軽にお寄せ下さいね!


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e9251d.efeb715b.40e9251f.37760879/?me_id=1212926&item_id=10000443&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmorihan%2Fcabinet%2Fsugoude%2F08745802%2Fthum_4_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e9251d.efeb715b.40e9251f.37760879/?me_id=1212926&item_id=10000788&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmorihan%2Fcabinet%2Flp%2Flp_hatimitsu%2F01-2024.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント