酪農は長年にわたり、私たちの日常生活において欠かせない存在として位置づけられてきました。
しかし、今日、世界の酪農業界は大きな転換点を迎えています。
昨年、大きな反響があった「うしおじさん」の倒産など、国内では酪農業が存亡の危機を迎えています。
一方で酪農ビジネスにおいて勝ち組と思えたニュージーランドも、地球温暖化という世界的な課題の解決や労働者不足のため混乱しています。
このままでは国内の新鮮な牛乳はおろか、輸入品の脱脂粉乳ですら手に入れることが出来ない未来が現実のものとなってしまうかも知れません。
そんな未来を回避する方策が我々に残されているのでしょうか?




どうぞ最後までご覧くださいね
日本の酪農が抱える課題
日本では、小規模酪農家が生産コストの上昇や市場競争力の低下に直面しています。
また、後継者不足という深刻な問題も浮上しています。
酪農を支える若手が減少する一方で、国際的な競争が激化し、国内市場での地位を維持することが困難になっています。
これを解決するスマート酪農などが産学共同で開発されていますが、導入のためには多額のコストと時間が必要であり、短期間での改善は非常に難しい状況です。
ニュージーランドにおける状況
世界的な乳製品の輸出国であるニュージーランドもまた、厳しい現実に直面しています。
政府は2030年までにメタンガスを10%削減し、2050年までに24~47%の削減を目指す野心的な目標を掲げています。
実はメタンガスは炭酸ガス以上に地球温暖化を促進してしまう物質なのですが、その生成は天然ガスの採掘現場よりも家畜が発する「げっぷ」や「おなら」の方が多いとのことです。
その研究結果を受けて、COP26(第26回気候変動枠組条約締約国会議)の場で2030年までに30%のメタンガスを削減するという国際的な合意がなされ、ニュージーランドもそれに賛同したのです。
しかし、この環境目標を達成するための政策である「げっぷ税」の導入は農業界の反発を受け、2025年早々に施行が予定されてましたが遅れることとなりました。
なお「げっぷ税」の骨子は「飼育頭数に応じた租税」と「適切な飼料への変更」ということで酪農家の経営を直撃する内容となってます。
これに加えてニュージーランドでは、若者の酪農業離れや労働者不足が深刻な問題です。
オーストラリアが提供する高収入の職に魅力を感じるニュージーランドの若者が、隣国に移住することで、さらに国内労働力が減少するという悪循環も見られます。
また日本と同様に「汚い」「きつい」「くさい」という酪農業は若い層から敬遠され、IT分野やデジタル関連に就業する人が増えていて、既に同国においてIT産業は酪農業に次ぐ収益性の高い分野となっているとのことです。
このような状況下では、環境負荷軽減のための取り組みである植林活動をする労働力の確保すら十分に行えないという現実があります。
酪農大国 中国の急成長と戦略的改革
中国では、かつて牛乳を飲む習慣が一般的ではありませんでした。
しかし、国家戦略のもとで酪農業が発展し、2023年にはインド、アメリカに次ぐ、世界第3位の生乳生産国となっています。
ほぼ全量が国内の乳児用粉ミルクや練乳などの加工品として消費されており、たった0.1%相当分が香港や台湾へ輸出されてます。
この成長の背景には以下のポイントがあります:
- 大規模化への取り組み:2000年頃から300頭以上の乳牛を飼育する酪農家に補助金を集中させ、大規模化を推進。
- 技術革新と品質向上:コールドチェーン技術の発展により、ロングライフ牛乳ではないフレッシュな牛乳の供給が可能に。
- 政策の影響:中小規模酪農家が淘汰される一方で、大規模酪農家が競争力を高め、効率的な生産を実現。
中小規模の酪農家に見切りをつけた改革が、中国酪農業の生産量を世界第3位に引き上げました。
その中国は10年前の生乳自給率が80%ほどだったのに、生乳の生産が急増しているにもかかわらず直近のデータでは自給率が66%と低下しており、国内消費量の伸びが異常に大きいことが伺えます。
中国が生乳を輸入しているのはニュージーランドが1位とのことですが、ニュージーランドの酪農の将来の危うさは先ほどお話した通りです。
日本が生乳をニュージーランドから輸入量を増やすのは難しくなる一方でしょう。
酪農大国 アメリカの抱える課題と将来
アメリカの酪農業の現状
アメリカはインドに次ぐ、世界第2位生乳生産国であり、その効率性と規模の大きさで世界市場にも影響を与えています。
アメリカの酪農場は大規模化が進んでおり、多くの乳牛を抱えるファームが中心的な役割を担っています。
近年では家族経営から企業型経営へとシフトする動きも見られ、これにより生産性向上が図られています。
しかし、現状には課題も多く存在しています。
日本やニュージーランドと同様に、労働力不足が深刻な問題として挙げられます。
やはり若い世代が酪農業を敬遠し、労働市場での人材確保が難航しているのです。
またインフレや燃料価格の上昇がコスト構造に影響を与えており、酪農家の収益性に直接的な打撃を与えています。
さらに、環境問題への対応も重要なテーマとなっています。
特に家畜から発生するメタンガス排出の削減が国際的な目標として掲げられており、これに向けた技術革新が進められていますが、先行投資が嵩んで飼料価格が高騰する等、儲かりにくい稼ぎにくい状況になっているのです。
アメリカ国内市場の状況
アメリカ国内における牛乳の需要は、近年多様化が進んでいます。
特にオーガニック乳製品や乳糖フリー製品、特定の栄養素を強化した製品の需要が増加しています。
一方で、人口が増加しているアメリカにおいて、従来の牛乳の消費量は伸び悩んでおり、植物由来ミルクの人気が牛乳市場に影響を与えています。
アーモンドミルクやオーツミルクなどの代替乳製品は、健康志向や環境意識が高まる消費者に支持され、特に若い世代を中心に普及が進んでいます。
牛乳市場が多様化する中で、価格競争も激化しています。現在の牛乳1ガロン(約4リットル)の平均価格は約4ドル程度ですが、植物由来ミルクは6〜8ドルと割高です。
それでも消費者の需要は価格を超えて環境や健康への価値観を反映しており、牛乳市場の頭打ちを引き起こす要因となっています。
また、国内消費が伸び悩む一方で、アメリカの乳製品輸出は増加しています。
2022年には、生乳生産量の約18%が輸出され、特にメキシコや東南アジア、中国といった海外市場が成長を牽引しています。
このように生乳の国内市場が停滞する一方で、国際市場の需要に支えられているのが現状です。
アメリカの酪農業の将来
アメリカの酪農業の将来は、いくつかの重要なテーマに左右されると考えられます。
一つ目は、労働力問題の解決です。
若者の酪農離れに対処するため、労働環境の改善や技術革新が必要です。
例えば、ロボット技術の導入やスマート酪農の実現が、労働力不足を補う手段として注目されています。
二つ目は、環境問題への対応です。
メタン排出削減をはじめとする持続可能な生産へのシフトが重要です。
アメリカではすでに飼料添加物の活用などが進められており、今後さらに普及が期待されています。
ただし、これには経済的なインセンティブや政策的な支援が欠かせません。
三つ目は、市場の多様化と輸出戦略の強化です。
国内消費の停滞を補うため、国際市場での競争力をさらに高める必要があります。
アメリカの乳製品は品質の高さで知られており、これを武器に新たな市場を開拓することが求められています。
総じて、アメリカの酪農業は国内外での課題に直面しながらも、技術革新や政策の力で新しい成長の可能性を模索しています。
これらの取り組みが成功すれば、持続可能で競争力のある産業としての未来が開かれるでしょう。
もしかするとAIなどに匹敵する成長産業となるかも?というのは期待し過ぎかもしれませんね。
世界最大の酪農大国 インドの現状と課題
インドは現在、世界一の牛乳生産国として注目を浴びています。
その成功の背景には、伝統的な小規模酪農を活用した独自のアプローチがあり、他の大規模酪農を進める国々とは一線を画しています。
しかし、この輝かしい成長の裏には、さまざまな課題も存在しています。
小規模酪農が支える酪農業
インドの酪農業は、主に小規模酪農家によって支えられています。
この特徴的な産業構造は、インド特有の社会的・文化的背景に基づいています。
たとえば、多くの家庭が牛を飼育し、自家用と地域市場向けに牛乳を生産しています。
また、牛乳はインド料理や宗教儀式に欠かせないものであり、その需要の高さは文化的背景と密接に結びついています。
特に注目すべきは、水牛乳の存在です。
水牛乳は、インド特有の乳製品生産を支える重要な要素であり、脂肪分が高いために特定の乳製品や伝統料理に広く使用されています。
この水牛乳は国際市場では一般的でないため、輸出向け産業としては限界があります。
ホワイト・レボリューションがもたらした成果
1960年代に始まった「ホワイト・レボリューション」は、インド酪農業の歴史を大きく変えました。
この政策によって、酪農協同組合の設立や技術革新が推進され、生産性が飛躍的に向上しました。
同時に、農家への補助金や技術支援が行われ、小規模酪農家がより効率的に生産を行える環境が整備されました。
水資源と土地利用の課題
しかしながら、インドの酪農業が直面する最大の課題は、水資源の不足と土地利用の問題です。
インドでは水不足が深刻であり、農業用水として利用される地下水の過剰な汲み上げが問題となっています。
また、急速な都市化によって牧草地が減少し、土地劣化が進行しています。
これらの課題に対処するため、インドでは効率的な水資源管理技術の導入や、環境に配慮した持続可能な土地利用が求められています。
消費の増加と輸出の可能性
さらに、インドの人口が世界最大規模に達したことで、国内の乳製品需要は急増しています。
この増加分を賄うための生産量拡大が必須ですが、現状では国内需要を満たすことが優先され、輸出向け生産はほとんど行われていません。
そのため、インドが乳製品の輸出国となる可能性は限られています。
大規模化への挑戦
大規模酪農家を育成するという選択肢もありますが、インド特有の水資源や土地の制約、小規模酪農家が社会的・経済的に重要な位置を占めている現状では、全面的な大規模化は現実的ではありません。
しかし一部では、モデル的な大規模酪農プロジェクトが試行されており、効率的な資源利用や新しい経営方法の可能性が探られています。
世界から酪農は消えるのか?
日本や海外から完全に酪農が消えるとは思えません。
地域によっては、文化や伝統が酪農を支え続ける場合もあるでしょう。
高付加価値な製品や技術革新が伴えば、酪農を新しい形、贅沢品として存続させる可能性も考えられます。
しかし、環境に負荷を与えない飼料への切替や労働者不足を補うための機械化などにより、安価で乳製品を愉しむのが難しくなる一方なのは間違いないようです。
日本人パティシエが世界で活躍してますが、多くのデザートが超高級品となり庶民では手の届かない存在となりえます。
代わりに植物由来製品が取って代わる可能性が高まっています。
実はそんな将来を見越して豆乳やナッツミルク、さらには植物性チーズなどの代替食品(ヴィーガン)は、徐々にそして着実に、特にアメリカの消費者の間で支持を広げてます。
結論:私たちが考えるべきこと
日本のそして世界の酪農業界は今、変革と存続の岐路に立っています。
その未来を形作るのは、私たち消費者の選択や、業界全体での革新と環境適応の取り組みです。
少しでも長く生乳由来の「抹茶フラペチーノ」などのデザートを味わうためには、その生産・流通コスト構造が値上げ不可避であることを認識し、相応の対価を支払う心構えが必要です。
ご存知の通り、抹茶は外国人を含む転売ヤーの餌食となり既に供給が滞ってます。
今、「抹茶スイーツ」を楽しまなかったら、来年はもう頂くことが出来なくなっているかも知れないですよ。
ウナギやサンマ、そしてイカも希少となり食べる機会が減りました。
乳製品由来のデザートも同じ道のりを進んでいるということに、私たちは危機感を持つべきです。
私たちが出来ることは、生き残りを賭けて植物由来の代替食品に対して積極的に取り組んでいる企業へも、経済的支援と同時に技術開発の一助となりえる行動が必要となることでしょう。
その代替品は最初から美味しいものを安価で生産できるはずはないですから、将来への投資として割り切って、あえて「高い」「まずい」ものでも購入する姿勢が必要です!
そうして将来の日本の食文化を支える企業を育てることが私たちの世代の課題かも知れません。
そのほか、新しい未来を築くために何ができるのか、一緒に考えていきませんか?




最後までご覧頂き感謝・感謝です。
ご意見やご感想、いつも有難うございます。
引き続き応援のほど、宜しくお願いします!



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4100af38.f2911e78.4100af39.9293b7d5/?me_id=1368502&item_id=10000040&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-cheese-fiano%2Fcabinet%2F06395919%2Fimgrc0104558381.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464081c7.44beb209.464081c8.ba7d07f8/?me_id=1311452&item_id=10000041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbussanten%2Fcabinet%2F08454583%2F08514500%2Fimgrc0080244818.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464084dc.23d76e11.464084dd.d4b03616/?me_id=1211862&item_id=10000008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgyokkado%2Fcabinet%2Fcart%2Fimgrc0075656112.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46408999.2f763d3c.4640899a.6dd54c3e/?me_id=1203694&item_id=10002547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Ffrantz%2Fphoto%2F640%2Fcheese-07-04-0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
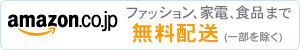
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46408b1b.20586f55.46408b1c.bdd0c09e/?me_id=1278352&item_id=10000191&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fthreenice%2Fcabinet%2Faiga-%2F100001912310.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46408f52.400c709a.46408f53.e13a393e/?me_id=1208201&item_id=10000614&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fprofoods%2Fcabinet%2Fr_shouhinup04%2F1030410_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464090d4.7958382d.464090d5.1f8bdda0/?me_id=1208420&item_id=10020301&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkyunan%2Fcabinet%2Fbicosume%2F04655588%2Fmirainomilk850.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464093a8.c42c71ea.464093a9.90852a55/?me_id=1343179&item_id=10000120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frawraw%2Fcabinet%2F07251293%2Fmatcha%2F12_matcha_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464093a8.c42c71ea.464093a9.90852a55/?me_id=1343179&item_id=10000032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frawraw%2Fcabinet%2F07213832%2F07213835%2Fkuri_tart_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e9251d.efeb715b.40e9251f.37760879/?me_id=1212926&item_id=10000098&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmorihan%2Fcabinet%2Flp%2Flp_kururu_set%2Fsakura_set_24_fv.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e8e85a.5178d522.40e8e85b.971d76af/?me_id=1195124&item_id=10002103&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitohkyuemon%2Fcabinet%2Fmail2021%2Fpage25%2Fhahatake25-011.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e8e85a.5178d522.40e8e85b.971d76af/?me_id=1195124&item_id=10000084&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitohkyuemon%2Fcabinet%2Fkago%2Fnamachoco5tubu.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
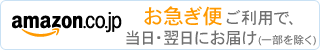
コメント