ヘルシー志向や日本文化への関心の高まりの中で、多くの外国人にとって抹茶は単なる飲み物ではなく、彼ら独自の食文化の一部として定着しつつあります。
しかし、その背後には、もう一つ、もっと深い光――言い換えれば、憧れが存在しているのではないでしょうか?
それは、茶道という日本の精神文化への関心の広がりです。
映画『日日是好日』の制作に原作者でありながら「技術指導」として携わるという異例の体験をした作家 森下典子さんが著したエッセー『茶の湯の冒険』では、この作品が映画化されて高く評価されるに至った、数多くの仲間たちとの日々が生き生きと描かれています。
私たちが思っている以上に、経済的な光(抹茶の需要)と精神的な光(茶道への憧れ)が、茶業界や日本文化の未来を照らす希望の源となっているのです。

どうぞ最後までご覧くださいね。
『茶の湯の冒険』に興味を持った理由は?
私はサラリーマン時代には競合会社の分析や業績管理などの実務も担当していたことから、老舗茶舗の経営破綻について記事を書く際にも、最低限の視点は持ち合わせていると思っています。また40歳で早期退職し、自営農家を10年間営んでいたので、業種は違えど、茶葉の生産者のご苦労は少しは理解できるつもりです。
これまでに、茶葉農家の苦労や茶舗の倒産といったテーマを扱う中で、茶業界の厳しさや現実はある程度お伝えできたかな、と思ってました。
でも、「茶道を嗜む『茶人』とはどんな人たちなの?」と問われると、まったくの未知の領域でした。
「きっと住む世界が違う人たちなんだろうな」と、どこか距離を感じていたんです。
ところが、森下典子さんのエッセー『茶の湯の冒険』を読んで、その印象ががらりと変わりました。
映画『日日是好日(にちにちこれこうじつ)』の技術指導として、“本物の茶道”を映像でどう表現するか。
その役割を任された「原作者」であり「茶人」の森下さんが、監督やスタッフに囲まれながら茶道指導責任者としてOK・NGを出す立場に置かれたとき―「見えない手で内臓をギューっとつかまれてる感じがした」と語るその描写に、私は思わずうなずいてしまいました。
それはまさに、生産者や経営者、そして現場責任者や営業担当者など、責任ある職を経験した全ての人が新しい挑戦に向き合うときに感じる“正体が見えない責任への不安”に通じるものがあったからです。
この本は、単なる“茶道エッセーの映画化の裏話”ではありません。
スペシャリストとして何かを背負って働く人たちが、共通して感じる緊張感と誇り―
そうしたものが丁寧に描かれている一冊だと思いました。
✿ エッセー『日日是好日』あらすじ
――登場人物と“人生哲学”を織り交ぜて
20歳の春、
「私」は母の勧めで、従妹の美智子と一緒に近所の茶道教室に通い始めます。
目的もなく始めた稽古。最初は「ただの型の繰り返し」のように感じられました。
けれど、そこにはひときわ静かな存在感を放つ年配の女性、お師匠さんがいました。
厳しくもなく、けれど一つ一つの所作に凛とした芯が通っていて、ふとした言葉が、心に深く残ります。
「雨の日は、雨を聴くのよ」
この言葉が象徴するように、お師匠さんの教えは
“その瞬間にしか出会えないもの”へと心を澄ませる感性を養ってくれました。
季節ごとに変わる道具や和菓子に触れながら、
「私」はいつしか、“今”という時間の尊さを体で覚えていきます。
それはやがて、就職、失恋、家族の死といった人生の節目に直面したとき、
静かに自分を支える“内なる柱”となっていくのです。
従妹の美智子は、途中で教室を離れ、
「私」はひとり、20年以上も稽古を続ける道を選びます。
静かに、でも確かに変わっていく日常の中で、
「私」は茶道の奥に、人生のすべてが詰まっていることに気づいていきます。
このエッセーは、単なるお点前の手順や作法ではなく、
その奥にある “生きること”の哲学 を、そっと手渡してくれる一冊です。
読後、心のどこかに、静かな余韻が残ることでしょう。
映画『日日是好日』が、特別だった理由は?
現代劇で初の茶道の映画という挑戦
これまでにも、千利休をはじめとする歴史上の人物を描いた時代劇で「茶の湯」のシーンが登場することはありました。
でも、そうした場合は「昔の作法だから」ということで、ある種の曖昧さや演出の余地が許されたんだと思います。
ところがこの『日日是好日』は違いました。
現代に生きる女性が、20年以上にわたって茶道を学び続ける様子を描いた、まさに“今を生きる私たち”の物語です。
つまり、そこに登場するお点前や所作が“本物でなければならない”。
それを観る人の中には、茶道の心得のある方もきっといる。
「一言、文句を言ってやろうという人も必ず現れる」。
そんな危機感から、森下さんは最初、技術指導の依頼を一度断ったそうです。
──それでも、引き受けたのはなぜ?
それは、お師匠さんの一言でした。
「そんなことを気にしていたら、何もしない人生を選ぶのと同じよ」
この言葉に背中を押され、森下さんは覚悟を決めます。
きっと、これがタイトルに「冒険」という言葉を選ばれた理由だろうなと思います。
映画スタッフとの交流
“本物の茶道”をきちんと伝えるという使命感のもと、ずぶの素人だった監督やスタッフさんたちに、茶道の奥深さと所作の意味を伝えていく過程が、とても丁寧に描かれています。
恐らく茶道体験をされた方にとっては、「あるある」なシーンが満載だと思いますよ。
主演女優 樹木希林さんの素顔
中でも印象的だったのは、主演の樹木希林さんとの結婚観に関する交流エピソードです。
森下さんが60代にして独身であることを知った樹木さんが、「お一人の人生は困ることが多いでしょう?」と尋ねたとき――森下さんは「結婚は困ることが多いでしょう?」と喉まで出かけた言葉を、ぐっと飲み込んだそうです。
このやり取りに垣間見えるのは、茶道に通じる“間”や“心得”といった、技術とは別の深い人間性です。
そしてネタバレになるので詳しくは書けませんが、樹木希林さんが「ある大切な茶道のシーン」に向けて、あまりにも“マイペース”な姿勢を貫く様子にも注目です。撮影日が迫っても稽古に取り組もうとせず、スタッフたちがやきもきする中、撮影現場での空き時間にはテレビのワイドショーを見ていた――。
そのとき、森下さんはどんな思いで彼女を見ていたのか。
そして、樹木希林さんが最後に見せた“本物の女優魂”とはどんなものだったのか。
このエピソードの続きは、ぜひ本書で確かめてみてください。
エンドロール 裏方さんたちの晴れ舞台
そしてこの映画の裏側をつづったエッセー「茶の湯の冒険」の真骨頂が、関係者試写会の席の描写です。
映画本編の最後、試写会のスクリーンに流れ始めたエンドロール。
そこには、森下典子さんの中で特別な意味を持つ「もう一つの物語」が静かに始まっていました。
“技術指導”という肩書きのもとに参加した映画制作は、普段「孤独な創作」に向き合う物書きの世界とはまったく異なるものですよね。
たくさんの人と意見を交わし、思いを重ねながら、一つの作品を形にしていく―その過程は、森下さんにとって新鮮で、時に緊張感に満ちた体験でもあったと容易に想像できます。
そして迎えた完成披露の場なのです。
スクリーンに流れるスタッフたちの名前を目にしながら、一般の方から見たら「単なる文字の羅列」が森下さんの中では次々と“生き生きした、あの瞬間のあの顔”の記憶へと変わっていきます。
それはまるで、舞台裏で黙々と支えてきた人々が、静かに表舞台に立ち並んでいくような感覚だったことだと思います。
観客にとっての「終わり」を意味する「エンドロール」が、作り手にとっては「積み重ねてきた時間の結晶」を味わう、ひときわ豊かな時間だったのです。
まさに「冒険」の末で見つけた宝物ですね。
森下さんがその一つひとつの名前に心からの感謝を重ねている様子が、読んでいるこちらにも自然と伝わってくる――そんなあたたかいエピソードです。
まとめ 映画版・エッセー、共に「日日是好日」の大ヒットが導く未来
映画『日日是好日』は、2018年に公開されて100万人の観客動員、興行収入10億円という目標をしっかりと達成し、国内の多くの人々の心に届いた作品となりました。
森下典子さんが描く原作の世界観の素晴らしさと、その実写化に尽力されたスタッフや関係者の皆さんのお力の結果です。
この作品が遺作となった主演の樹木希林さんも大変喜んでいらっしゃることだと思います。
茶道を既に身につけられている方にとっても、そして茶道体験から始めたいと考えていらっしゃる方にも、この本や映画をみることで、ますますその気持ちが昂るはずです。
さらに原作エッセー『日日是好日』は、韓国・フランス・イギリス・フィンランド・イタリア・オーストラリアなど、世界中から翻訳出版のオファーが相次いでいるそうです。
「抹茶」というキーワードが食と健康の観点から注目を集めている今、そこにある精神文化―茶道の“こころ”を伝える物語も、このエッセーを介して静かにそして確実に世界に広がりつつあるのです。
日本の茶業界は今、かつてないほど大きな変化と試練の時を迎えています。
けれども、経済の光(抹茶需要)と文化の光(茶道への憧れ)という両輪が、これからの未来を照らしてくれると私は信じています。
まさに日日是好日(にちにちこれこうじつ)ですね!




既に映画を観た方も、まだの方も楽しめる本ですよ!
映画での樹木希林さんの演技、すっごく楽しみです。

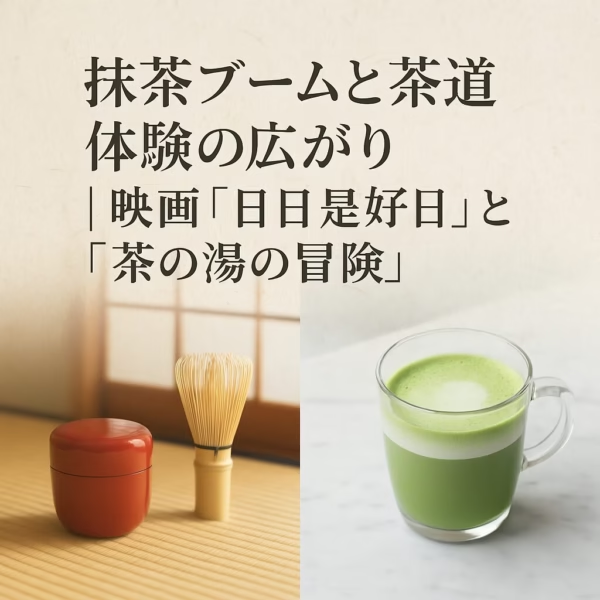
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d8f481b.684b1bea.3d8f481c.2b2282bf/?me_id=1213310&item_id=21163154&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1934%2F9784167921934_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント