コメが足りない――なのに「在庫はある」と言われる。
スーパーでもふるさと納税でも、米は品薄で価格は高騰。
この矛盾の裏でいま、日本のコメ流通に何が起きているのか?
本記事では、価格を動かす「買い占め」や「出し惜しみ」の実態、
そしてそれを見えなくしている制度の限界と構造的な問題に切り込みます。
消費者も生産者も納得できる流通改革の第一歩を、一緒に考えてみませんか?
はじめに
「スーパーでコメが高すぎて買えない」「ふるさと納税でもコメの予約が殺到」——。
いま、日本中で”コメ不足”の声が広がっています。農林水産省は「在庫はある」と発表し、2025年春には備蓄米15万トンを市場に放出しました。しかし、それでも米価は下がらず、消費者の不安も沈静化していません。
なぜ「在庫があるのに買えない」のでしょうか?
一見不思議なこの現象の裏には、流通段階での“買い占め”や“出し惜しみ”といった行動が、構造的に把握されていないという、日本の旧態依然とした仕組みがあるように思われます。
【問題の核心:流通段階で何が起きているのか?】
コメが高騰する中、実際には農家の倉庫や集荷業者、大手卸の保管倉庫には一定量の在庫が存在しています。しかし、それが市場に出てこない。
これは、価格のピークを狙って“売り控え”をする業者が存在するからです。政府が備蓄米を放出しても、「価格が崩れる」と見た業者が自前の在庫を出さない限り、市場に出回る供給量は増えません。
つまり、需給の問題ではなく、心理と仕組みによって“コメの流れ”が詰まっているのです。
私は「買い占め」という行為自体を一概に悪と断ずることはできません。企業や流通業者が市場動向を見越して在庫を確保するのは、マーケティングの一環として当然の経済行動とも言えます。私たち消費者もまた、「数量限定」「期間限定」といった“今買わなければ手に入らない”という不安を煽る広告に日常的に接しており、それに反応して購入行動をとっています。
問題なのは、それらの行為が“見えるかたちで説明されず”、結果として“市場を支配する手段”となってしまう点にあります。誰がどこにどれだけの在庫を保有しているのかが分からないまま、価格形成に影響を与える状況は、消費者の不信感と過度な不安を呼び起こします。
つまり、“買い占め”そのものではなく、その行動の“影響範囲”が大きくなり、かつ実態が不透明なまま進行することが問題なのです。それによって市場の健全性が損なわれ、消費者の信頼が失われる。この構造的な歪みこそが、本質的な課題と言えるでしょう。
私たちの代表である国会において、こうした在庫の偏在や出し渋りが国民の不安を招く問題であると正式に認識されるのであれば、その状態を是正するために、出荷の促進や在庫情報の開示を求める法律を準備することは、十分に正当な政策判断といえるでしょう。
その際には、許認可事業者であるコメ流通業者に対して、在庫情報の報告義務を課すことも、公的指導として合理的かつ必要な措置と認められるはずです。
【仕組みの限界:なぜ監査できないのか?】
前章で述べたように、コメ流通における在庫の偏在や出し渋りは、必ずしも違法ではなく、経済合理性のある判断ともいえます。しかし、それが社会不安を招き、制度的にもチェック機能が働かないとなれば、やはり問題は“仕組みの側”にあります。
日本のコメ流通業は登録制度があるものの、実際には届出と年1回の報告のみ。抜き打ち監査や在庫調査は行われず、ペーパーカンパニーや隠し倉庫を利用すれば、在庫を隠すことも容易です。
さらに問題なのは、こうした業界団体や卸業者の中には、農水省OBの天下り先となっている法人も存在することです。調査対象が身内であれば、本気の監査が働かないのは当然です。
制度は存在していても、それが十分に機能していない。これが現在のコメ流通制度の限界です。
【私ならこうする:「信用の見える化」改革案】
私が農政に関わる立場にあったとしたら、まず着手したいのは「在庫と販売予定の見える化」です。
- 卸・集荷・倉庫業者に対し、リアルタイムで在庫を登録・更新する「デジタル在庫台帳」の導入
- ランダムな実地監査と、虚偽報告への補助金停止・営業制限といった強制力のある罰則
- 正直な業者には「政府公認の信頼マーク」を与え、備蓄米や政府調達の優遇枠を提供
ズルができず、まじめにやる人が報われる仕組みを整えることこそ、今の農政に必要です。
【結論:問うべきは“仕組み”である】
日本では、農家の高齢化と後継者不足が深刻化しており、今後のコメ生産量は確実に減少していくと見られています。人口減少による需要の変化と併せて、適切な生産・輸入量の見極めには、まず現在のコメ流通の透明性が不可欠です。主食であるコメの安定供給を守るためにも、「見える流通構造」の構築は待ったなしの課題です。
いま日本のコメ流通は、供給量そのものよりも、仕組みの不透明さによって混乱しています。
コメ不足の諸悪の根源は、流通段階での買い占め・出し惜しみが、監査されないために正確に把握できない旧態依然とした構造にある。
制度は存在していても、それが十分に機能していない。だからこそ「信用の見える化」が今こそ必要です。消費者が安心し、生産者も報われる流通の再構築に向けて、私たちはこの構造の問題に目を向けるべきではないでしょうか。
私は、長年米価が据え置かれてきたことを重く見ています。今の価格上昇は、ようやく農家が適正な対価を受け取るチャンスであると考えています。だからこそ、この機に利益を中間で留める流通構造から、労力に見合った利益分配を実現する見直しが必要だと考えてます。
追記 江藤農相が輸入米の主食用枠拡大案に反対!
2025年4月18日、農水大臣が「コメの輸入拡大はしない」と明言しました。
一見すれば「国産農業を守る」という言葉に聞こえますが、本当に守られているのは誰なのでしょうか?
皆さんの多くがすでにお気づきのように、「利権を抱えた既得権構造」そのものですよね。
国民の不安より、農水省OBの天下り先を守る身内の論理が優先されているのは明らかで、今回の発言は流通改革をしない宣言であり、一般国民だけでなく、まともに収益を得られていない農家も間違いなく被害者となるのです。
「在庫はあるが市場に出回らない」という歪んだ構造を放置したまま、“現場の痛み”には目を向けない政治に、いったい誰が共感できるのでしょうか?
私は国産のコメを守るというなら、“農家が報われる構造”を構築すべきだと思っており、今回の江藤農水大臣の発言に対して明確なNOを突き付ける必要があると思います。
これまで自民党に白紙の委任状を出し続けてきた農家の皆さんも、過去のご自身の投票行動を振り返り、7月の参議院議員選挙では、その一票に意味を持たせるべきです。
輸入米の主食用枠拡大案、江藤農相が反対 財制審が提案 – 日本経済新聞
 ピーチです!
ピーチです!最後までご覧頂き有難うございました。
コメ不足問題は根が深そうですね。
今解決しないと将来もっと困りそうです
皆さんの感想をお聞かせください

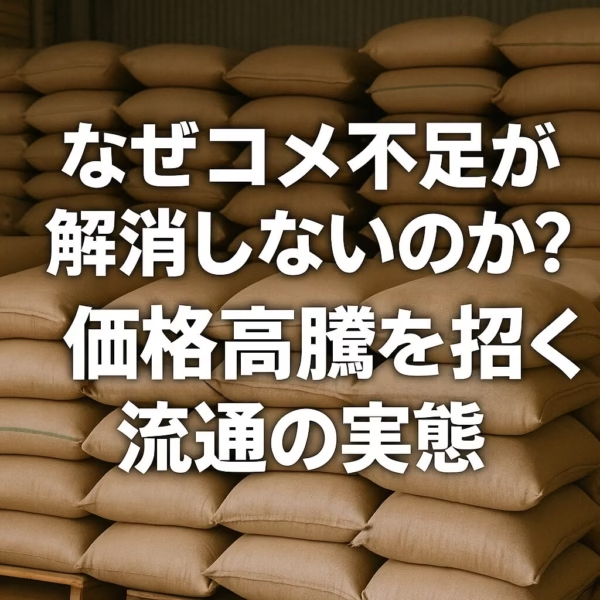
コメント