「ホクレンに出さないと補助金がもらえない」──そんな話を聞いたことはありませんか?
北海道の酪農家が抱える“自由なはずの出荷”と“縛られた制度”の矛盾。
年間売上5,000万円でも赤字に苦しみ、廃業へ追い込まれる現実。
本記事では、補助金の仕組み、ホクレンとの関係、そして制度再設計という選択肢について、現場の視点から丁寧に読み解きます。
はじめに
最近、SNSやネット番組を中心に「ホクレンは農家を搾取している」「全量出荷を強制してくる」などの声が聞かれるようになりました。中には有名インフルエンサーが「ホクレンが牛乳の価格を操作している」と断言する場面もありました。しかし、現場の実態はどうなのでしょうか? 本記事では、酪農とホクレンの関係について、制度の仕組みと現場の現実をもとに整理してみます。
1. ホクレンとは?──酪農家との関係
ホクレンは北海道内のJA(農協)を束ねる上部組織であり、その構成員であるJAには一人ひとりの農家が組合員として加入しています。つまり、ホクレンも最終的には“農家が出資している協同組合”です。
特に酪農分野では、ホクレンが「指定団体」として生乳(せいにゅう=しぼりたての牛乳)の集荷と販売を担っています。北海道では、ほぼ全ての酪農家が生乳をホクレンを通して出荷しています。
ホクレンの収入は組合費だけで成り立っているわけではありません。生乳や農産物の集荷・販売において、販売価格と仕入価格の差額(いわゆるマージン)や、流通・加工・保管といったサービスに伴う手数料が主な収益源です。この構造は商業的には一般的ですが、「農家から搾取している」との批判を受けやすい一因にもなっています。
この背景として、ホクレンには農林水産省や関連省庁からの天下りを多数受け入れているとの指摘もあり、組織の透明性や規模の適正さに対する不信感が一部で高まっていることが挙げられます。もしホクレンが本来の機能を超えて過剰に肥大化しているとすれば、それが批判を招いている根源かもしれません。
2. なぜ全量出荷するのか?──補助金と制度の仕組み
北海道の酪農家が本州と比べて約1.5倍の経産牛を飼っているにもかかわらず、それ以上の大規模化に踏み切れない背景には、経営リスクの問題があります。とりわけ家畜感染症のリスクは深刻で、過密な飼養環境では病気の蔓延が致命的になります。かつて豚熱の流行で壊滅的な被害を受けた神明畜産の事例(https://www.makoto-lifecare.com/pig-farming/)のように、一度感染が発生すれば廃業に直結するケースも少なくありません。そのため、リスク管理の観点から、あえて規模拡大を抑える酪農家も多いのが現実です。
北海道での酪農が大規模化しきれない背景には、感染症リスク以外にも複数の要因があります。まず、人手不足が深刻で、規模拡大に必要な労働力を確保することが難しくなっています。加えて、365日休みのない酪農業では、家族経営の労働限界を超えると外部雇用が必要となりますが、人件費負担が重く、収益性を圧迫します。
また、良質な放牧地やインフラの整った土地には限りがあり、牛舎や堆肥舎などの増設にも多額の初期投資が必要です。後継者不足も深刻で、将来の継承が見通せない中で大規模投資に踏み切れない酪農家も少なくありません。こうした多重の制約が、北海道の酪農の「もっと拡大できそうでできない」現状を作り出しているのです。
そして北海道の多くの酪農家は、単に牛乳を生産するだけでなく、子牛の繁殖や乳用種の肥育による肉牛生産も兼業しています。これにより経営の多角化を図り、乳価の変動や経費高騰といったリスクを分散しようとしているのです。その実態については、筆者の別記事(https://www.makoto-lifecare.com/hokkaido-beef/)でも詳しく紹介しています。
生乳をホクレンに出荷する大きな理由の一つが、国の補助金制度との関係です。日本では酪農経営安定のための制度がいくつか存在し、その中には「指定団体に出荷すること」が前提となっているものがあります。
つまり、ホクレンを通じて出荷することで、
- 経営安定対策(補助金)を受けられる
- 基準乳価の保証が受けられる
- 流通・保存・販売のインフラ支援が得られる
といったメリットがあります。一方で、ホクレンを通さずに販売する「指定団体外出荷」を行うと、
- 補助金が受けられない
- 市場価格にさらされ、価格が不安定
- 流通手段の確保が難しい
といったリスクが発生します。
ここで重要なのは、補助金はあくまでも「価格調整金」であるという点です。つまり、市場価格が基準乳価を下回った場合に、その差額の一部を補填する制度で、常に一定額が支給される生活補助のようなものではありません。
なお、この補助金の財源は当然のことながら、国費、すなわち私たちが納めている税金です。
ところで実際の北海道の平均的な酪農家では、年間売上が約4,700万円程度あるとされますが、飼料費や光熱費の高騰、設備投資、人件費などを差し引くと、経費の方が上回ってしまうケースも少なくありません。特に輸入飼料価格の上昇が重くのしかかっており、経費5,000万円超>売上4,700万円という「逆ザヤ」の構図に陥ると、赤字が常態化します。その結果、生活費は貯金を切り崩して捻出するしかなく、経営継続を断念して廃業に至る酪農家が後を絶たないのです。
3. 本当に自由に売れないのか?──制度的“強制”と現場の選択
形式上は、酪農家がどこに売るかは自由です。法律で「必ずホクレンに出せ」と決まっているわけではありません。ただし、補助金制度と連動していることで、結果的に“出さざるを得ない”という状況が生まれているのは事実です。
この構造を「強制」と見るか、「制度と支援の引き換え」と見るかは立場によって異なりますが、少なくとも現場の酪農家の多くは、安定した収入と販路を得るためにホクレンを通した出荷を選択しています。
4. 問題はどこにあるのか?──情報の不透明さと誤解
問題は、制度や流通の仕組み、価格決定や補助金の条件といった”酪農の経営構造そのもの”が、十分に説明されていないことにあります。「ホクレン=搾取」「農家は縛られている」といった意見が広まる背景には、制度や流通の構造についての情報不足と、現場の声が可視化されていないという問題があります。とくに、ホクレン自身やJA(農協)、さらに制度を設計・運用する行政(農林水産省など)が、出荷制度や価格形成のプロセス、補助金の仕組みについて農家や消費者に対して十分な説明責任を果たしていない節があります。
こうした不信感を払拭するためには、ホクレン自身が改善する必要があります。たとえば価格決定の透明性を高めること、出荷ルールを柔軟に見直すこと、そして農家との対話の機会を増やすことが求められます。「農家の組織」として原点に立ち返り、信頼を回復するための努力が必要とされている局面とも言えるでしょう。
そこまで実現すれば「ひろゆきさん」から「目の敵」にされなくなると思います、これ、私の感想ですけど。
5. まとめ──ホクレンは敵か、共存のパートナーか?
「ホクレンが農家を縛っている」「補助金目当てに全量出荷を強いられている」といった声がネット上で広まる背景には、制度や価格の仕組みが分かりづらく、現場の実態が十分に伝えられていないという構造的な問題があります。
そして実際の酪農経営は、売上が5,000万円近くあっても経費がそれを上回り、赤字を抱えながら貯金を切り崩して生活する──そんな“ギリギリの経営”が現実です。
そのなかで、ホクレンは農家にとって重要な流通インフラであり、命綱でもあるのですから、その存在は「敵か味方か」といった単純な対立ではなく、「制度の維持と改善の鍵を握る存在」として位置づけるべきかも知れません。
しかし、ここまで構造が複雑化し、制度不信が広がっているのであれば── いっそホクレンを一度解体して、農家に必要不可欠な部分のみ、つまり、「流通インフラに特化した中立的な新組織」として再出発させるという選択肢も、真剣に検討すべき時期に来ているのかもしれません。農家が主役となってサービスを選び、自立した経営判断ができる柔軟な仕組み。それこそが、これからの共存のかたちではないでしょうか。
離農者続出で崩壊寸前の北海道の酪農業、再建のために必要なのは対立ではなく、再設計の知恵なのかもしれません。
みなさんはどう思いますか?
 ピーチです!
ピーチです!最後までご覧頂き有難うございました。
是非皆さんのご意見をお聞かせください!
お待ちしてます

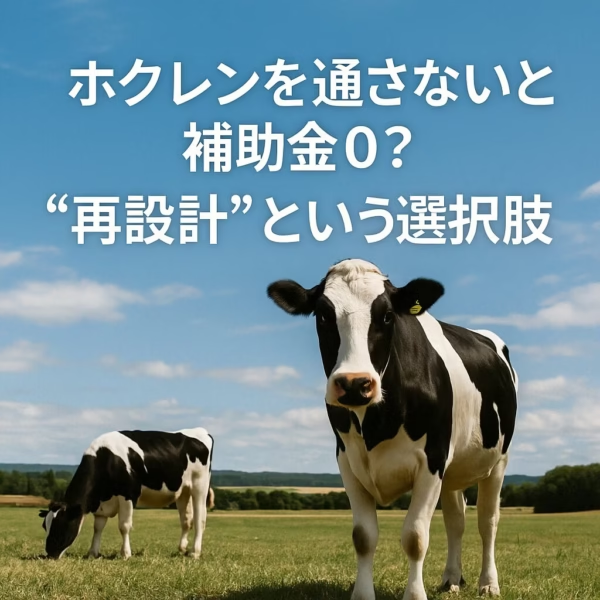
コメント