全国一位の荒茶生産量、国内最多の有機JAS認証面積、そして数億円規模の「てん茶」加工工場が続々と稼働開始──。
鹿児島県は今、世界に向けた抹茶輸出という新たな挑戦の真っ只中にいます。
鹿児島県では単に収穫量が多いペットボトル飲料用の茶葉の収穫量を増やしているわけではありません。
健康志向とともにグローバル市場での存在感を増す「抹茶」、その原料生産地として、鹿児島は国内においても、そして世界の中でも確実に台頭しつつあります。
本記事では、抹茶をめぐる世界的トレンドから鹿児島県の最新の取り組み、そして輸出先の動向や業界関係者の声に至るまで、今まさに動き出している“茶業の未来”を網羅的にお届けします。
 パンチです
パンチです静岡でもなく、京都でもなく
鹿児島県がお茶を牽引する存在になってきてます!
最後までどうぞご覧くださいね
1. はじめに
抹茶のグローバル需要の現状と可能性
抹茶は今や「ブーム」を超えて、世界的な「文化」として根付いてきています。
近年、抹茶市場は急速に拡大しており、将来的には1兆円規模の産業に成長する可能性が高いとされています。
その背景には、健康志向の高まり、スーパーフードとしての認知度の向上、さらに抹茶を使用した多様な製品(抹茶ラテ、スイーツなど)の普及があります。
アメリカやヨーロッパ、アジア市場を中心に、抹茶は既に食文化として確固たる地位を確立しつつあり、特にアメリカのカフェや健康志向層では日常的に取り入れられる存在になっています。
抹茶の需要が世界中に広がる中で、日本の茶産業は新たな収益源を求め、抹茶の原料となる「荒茶」や「てん茶」の生産体制を強化しているのです。
鹿児島県のお茶産業の重要性と成長
鹿児島県は、荒茶(てん茶)生産量が全国一を誇り、国内の抹茶市場において重要な位置を占めています。
この実績の背後には、数多くの取り組みが存在しています。
- 有機JAS認証面積が全国トップ
鹿児島県は、有機栽培茶の生産面積が全国トップを誇ります。環境への配慮や品質の高さが、国内外の消費者に対して大きなアピールポイントとなり、特に健康志向の高い消費者に人気があります。 - 輸出を意識した港湾インフラ(鹿児島港)
鹿児島港は、海外への輸出を視野に入れた重要な拠点です。港湾インフラの整備が進んでおり、輸出を行うための物流面でも優位性を持っています。これにより、鹿児島茶は国内のみならず、海外市場への流通がしやすくなっています。 - 若手農家や法人化が進みやすい生産体制
若手農家の参入が進んでおり、法人化された茶農家も増加しています。この動きは、効率的な経営を支えるだけでなく、抹茶の需要に応じた柔軟な生産体制を作り上げるためにも重要です。特に、規模拡大が可能な法人化の進展は、今後の生産能力を高めるカギとなっています。 - 数億円規模のてん茶加工工場の新設ラッシュ
鹿児島県では、抹茶の原料となる「てん茶」の加工工場が数億円規模で新設されるなど、設備投資が加速しています。これにより、より高品質で安定的な供給が可能になり、特に海外市場への輸出を視野にした生産・供給体制が整いつつあります。新設された工場のうち、6か所がこの1年の間に立ち上がっており、抹茶生産の拡大が現実のものとなっています。
2. 鹿児島県のお茶産業の現状
荒茶生産量、日本一の快挙
2024年、鹿児島県は荒茶の生産量で全国1位を獲得しました。
これまで長年トップの座を守ってきた静岡県を抑えての快挙であり、全国の茶業関係者からも大きな注目を集めました。
この結果は単なる一過性の現象ではなく、鹿児島県全体で進めてきた生産体制の改革と輸出戦略の成果の表れです。
「てん茶」への生産シフトが加速
この生産量拡大の裏には、煎茶から抹茶用の原料である「てん茶」への大きなシフトがあります。
てん茶は、通常の煎茶に比べて取引価格が約2倍と高く、しかも収穫前から買い手がつくほどの引き合いがあるため、農家にとっては非常に魅力的な作物です。
農家からは「これまで以上に安心して作付けできる」との声も上がっており、この動きは加速度がついて進んでいきそうですね。
地域全体で輸出対応を強化
鹿児島県では、輸出を前提とした茶業戦略が随所で展開されています。
たとえば港湾インフラの強化。鹿児島港をハブとした輸出体制が整備されつつあり、「地元で収穫された抹茶原料をそのまま鹿児島から海外に出荷する」という構想も現実味を帯びています。
実際に、2023年の鹿児島県の茶輸出量は約8,800トンに達し、そのうち約3割がアメリカ向けでした。
ところが、2024年4月9日から「トランプ関税」の影響で、これまで0%だったアメリカ向けの関税が24%に引き上げられ、業界内には不安の声も広がっています。
「せっかく日本一になったのに、頭の上からハンマーで叩かれたような感じ」
— 茶業関係者(MBC南日本放送・2025年4月10日)
とはいえ、高品質であれば価格に関わらず選ばれる可能性は十分にあるという意見もあり、関税の影響を抑える努力と同時に、ブランド力や品質向上への取り組みがさらに加速しています。
法人化・若手参入も追い風
鹿児島県のもう一つの強みは、「若手農家の参入」や「農業法人化」の進展です。
これは他地域と比較しても顕著な特徴であり、新しい品種への対応力や、てん茶向けの専用設備の導入など、生産現場の柔軟性・俊敏性に優れています。
また、有機JAS認証の取得が全国でも突出しており、環境と調和した持続可能な生産体制を築いている点も、海外市場での信頼性を高める重要な要素となっています。
この動きは低収入のため離農している全国の茶葉農家へ一石を投じる動きになるかと思います。
3. 抹茶市場の拡大
世界が注目する「抹茶」という市場
近年、抹茶のグローバル市場はかつてないほどの拡大を見せています。
日本貿易振興機構(JETRO)などの予測では、世界の抹茶市場は今後1兆円規模に到達する可能性があるとも言われており、日本国内の生産者やメーカーにとって大きなビジネスチャンスが広がっています。
抹茶の魅力はその多様性と健康価値にあります。
煎茶が主に日本国内向けだったのに対し、抹茶は世界80億人がターゲットになり得る飲料・食品原料です。
「抹茶はもはや“ブーム”ではなく、“文化”として世界中に定着しつつある」
— 茶業関係者の声より
アメリカではWhole Foodsなどの高級スーパーで抹茶が棚を占め、イギリスではPret a Manger(プレタマンジェ)などのチェーン店が抹茶ラテを定番メニューとして導入してます。
東南アジアでも富裕層を中心に「スーパーフード」としての人気が高まっており、抹茶市場は国境を超えた展開を見せています。
なお世界での抹茶の普及においては「ハーゲンダッツショック」と「スタバショック」なしでは語れません。
詳しくはこちらの記事をご覧くださいね。
荒茶(てん茶)の輸出金額は、ここ5年間で2倍に
この世界的な動きを裏付けるデータとして、荒茶(碾茶)を原料とした抹茶の輸出金額が、過去5年間で約2倍に増加していることが挙げられます。
これは、一過性のトレンドではなく、構造的な成長産業としての抹茶の位置づけを示す重要な指標です。
この安定した需要を背景に、静岡県や鹿児島県では数億円規模のてん茶工場の建設が相次いでおり、生産から加工、輸出に至るまで一貫した体制整備が進んでいます。
確実に儲けが期待できる産業への集中投資が好循環を導いているという、現代の日本の農業、産業では非常に貴重な成功事例であろうかと思います。
4. 宇治ブランドとの連携と独自路線の模索
老舗ブランド「森半」も注目する鹿児島産てん茶
鹿児島県のてん茶生産拡大において、既に高級抹茶の代名詞・宇治ブランドとの連携が進みつつあることは、注目に値します。
実際、NHK鹿児島放送局の報道によれば、京都の老舗「森半」ブランドを展開する共栄製茶が、鹿児島産のてん茶を原料に抹茶を製造していることが明かされました。
共栄製茶のように高品質な原料を求める加工業者にとって、鹿児島の安定供給力と大規模な生産体制は極めて魅力的。かつては「宇治」といえば京都産を指すのが通例でしたが、今や品質重視のブランドは産地の垣根を越えた選定を行っており、鹿児島のポジションは確実に上昇しています。
「共創」か「独自」か、産地の進路選択
こうしたブランドとの連携を深める一方で、鹿児島県内では「宇治ブランドに依存せず、鹿児島独自の抹茶ブランドを築こう」という気運も高まっています。県内に新設された6か所のてん茶工場では、自社名義で海外展開を模索する事業者も出ており、「産地イメージ」の自立が少しずつ進んでいる状況です。
とりわけ、有機JAS認証面積が日本一という強みや、輸出に最適な鹿児島港の存在は、宇治とは異なる価値訴求を可能にします。高温・多照な気候を活かした栽培サイクルの短さや、若手農業法人の積極参入といった柔軟性も、独自ブランド戦略に追い風を与えています。
宇治と鹿児島:競争か、共存か
「宇治 vs 鹿児島」という二項対立ではなく、高価格帯と中価格帯、ブランド重視と量産安定型といった多様な戦略が共存できる市場へと、抹茶の世界はシフトしています。
- 宇治ブランド:老舗の信頼、格式、伝統の高級抹茶路線
- 鹿児島ブランド:大量生産・輸出対応力、価格競争力、有機や若手の柔軟性
このように、それぞれが持つポジションを活かしつつ、市場全体の成長に寄与する形が理想的です。連携と差別化を巧みに両立できるかが、鹿児島県にとっての今後の鍵となるでしょう。
5. おわりに 鹿児島県から世界へ
全国一位の荒茶生産量、国内最多の有機JAS認証面積、そして数億円単位の「てん茶」加工工場が次々と建設される中、鹿児島県は今、抹茶輸出を見据えた新たなステージに立っています。
これらは決して偶然の産物ではありません。
若い担い手が次々と現れ、法人化によって柔軟な経営を可能にし、さらに港湾という物流インフラを背景に「海外」へターゲットを絞る。
この一連の構図こそが、「茶産地・鹿児島」の証であり、真の実力なのです。
宇治とも連携し、その知見とブランドをともに育てる道もあれば、南国鹿児島ならではの豊潤な土壌と気候、そして機動力ある生産体制をもって、独自の「Kagoshima Matcha」として世界市場を切り拓く道もありますよね。
抹茶はもはや一過性のブームではありません。
世界中で「スーパーフード」から「ライフスタイル」そして「文化」へと昇華・定着しつつあります。
そのグローバル需要の拡大は、荒茶(碾茶)を原料とした抹茶の輸出金額が5年間で倍増したという数字にも明確に表れています。
アメリカへの輸出が全体の3割を占める中、今回の「トランプ関税」による逆風も現れました。
しかし、これは単なる障壁ではなく、品質と信頼を武器にした新たなマーケティングの機会として捉えるべきかも知れません。
「緑茶はアメリカにはない飲料。だからこそ、価値を訴えることができる」。
まさにその言葉の通り、日本の茶文化はまだまだ広がる余地を世界に持っているのです。
京都にルーツを持つ老舗ブランドが脈々と紡いできた「抹茶の文化」。
そこに敬意を払いながらも、鹿児島はまた別の形で未来の担い手として台頭しつつあります。
鹿児島茶が、今、世界へ。
新たな時代が始まろうとしているのです。




最後までご覧頂き有難うございました。
鹿児島県が荒茶生産一位になったのは通過点!
世界で外貨を稼げる産業への成長が目的だったんですね。
みんなで日本のお茶産業を盛り上げていきましょう!
-




特集|抹茶ブームの裏側で起きていること──日本茶業界 崩壊と再生への道
日本茶業界の現状と再生への道のりをご紹介します。 -




高品質なのに、なぜ売れない?静岡茶の“本当の課題”とは
折角の高品質のお茶、もっと売れるにはどうしたら良いのでしょうか? -




まとめ記事 日本茶業界の「厳しい現状」、そして「将来への挑戦」
茶業界を取り巻く市場環境の変化は厳しく、私たちの支えが必要です。 -



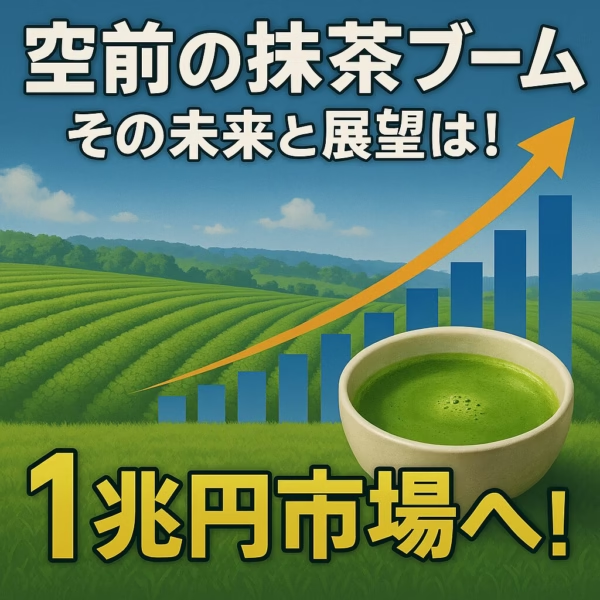
空前の抹茶ブーム その未来と将来への展望は
抹茶1兆円産業へのみちのりは! -




スターバックスが背負って立つ?抹茶グローバル化の未来
スタバの活躍で抹茶が1兆円産業に?

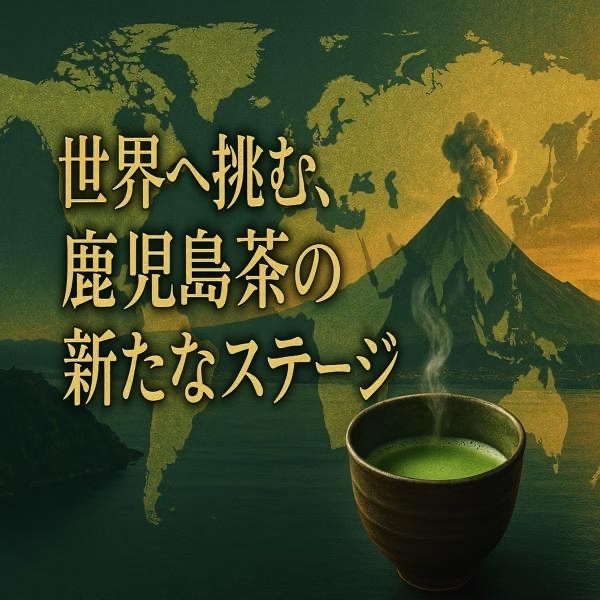





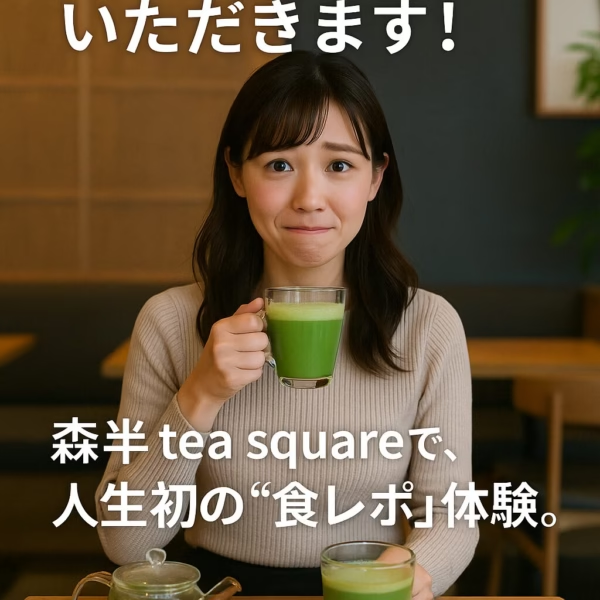
コメント